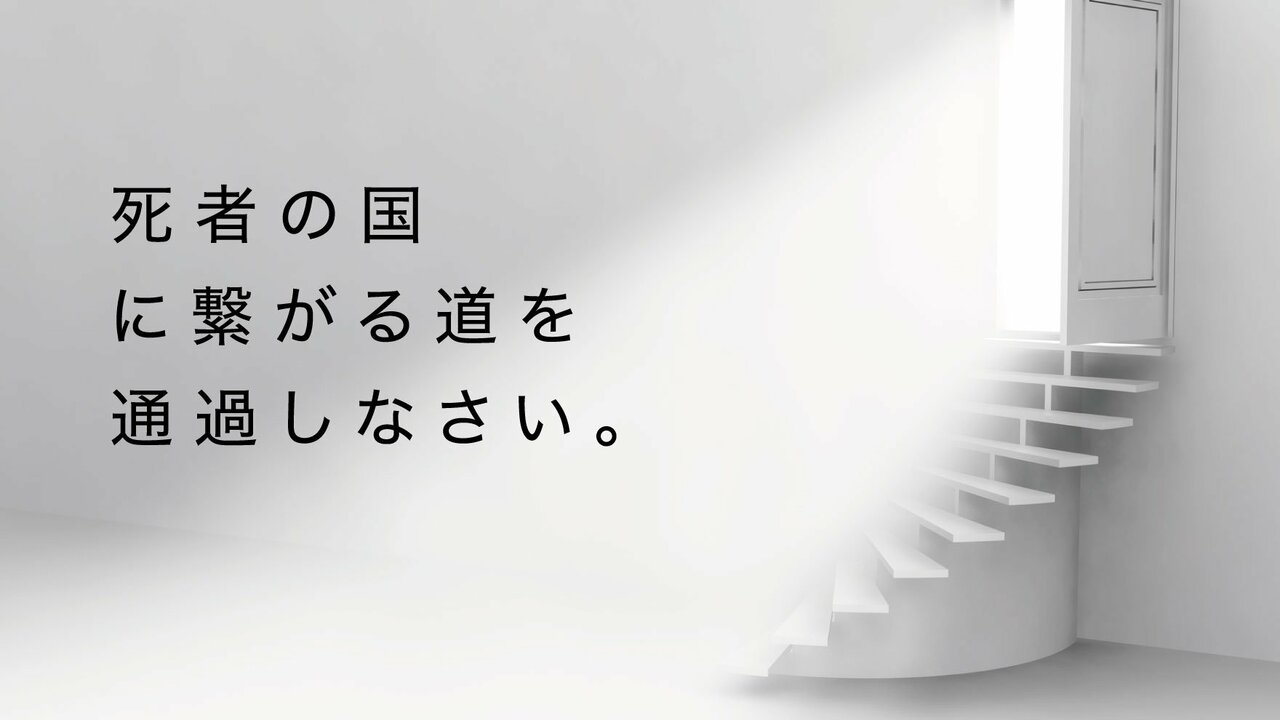このように夢の中で本来の自分を見せられるのは、ちょっと気恥しくて、何とも言えないものでした。自分の「霊」は、どんなに極端な物でも、「栄養のある」食べ物を無性に欲しがっていたのに、「小さないつもの」彼は、自分の手に負えないことに出会うと、つい、易しいほう、甘味のあるほうを選んでしまうみたいでした。
新しい体験に伴う痛みや打撃を恐れ、変化を恐れて、何とか自分は免れますようにといつも祈っているのでした。
「うーん、ぼくの中には、魂がどんなに求めていても、どうしても引いてしまうところがある。それは確かに褒められたことじゃないけど、ぼくの魂はぼくよりもはるかに勇気があって嬉しいな」
とフォールは思いました。
「まさにお前らしいじゃないか、フォール。何か学ぶことはあったかね?」
フォールは、ベッドから落っこちそうになりましたが、その表情には驚きと喜びが溢れていました。至高の神のとどろくような声が、彼の頭の奥深くから響いてきたのです。いきなり、しかも、思いがけなく! あぁ、なんて甘美な声でしょう!
「わぁ、戻ってきてくださったんですか!」
フォールは喜びの叫びを上げました。
「お前が戻ったんだよ」
至高の神は答えました。
「ぼくが? どういう意味ですか? ぼくはいつもいたし、耳を澄ませていたと思うんですけど」
「フォール、これはね、お前が何を考えているかではなくて、お前がどうあるか、なのだよ」
それは、フォールには少し謎めいた言葉でしたが、こんなに最高の気分の時に、またもや至高の神と哲学的な議論をしたくはありませんでした。
「どうせ、神さまにかなうわけないしね」
とフォールは、半ば面白がって、生意気なことを考え、思わず笑ってしまいました。それほど彼は幸せだったので、箸が転んでも、可笑しいと思ったでしょう。