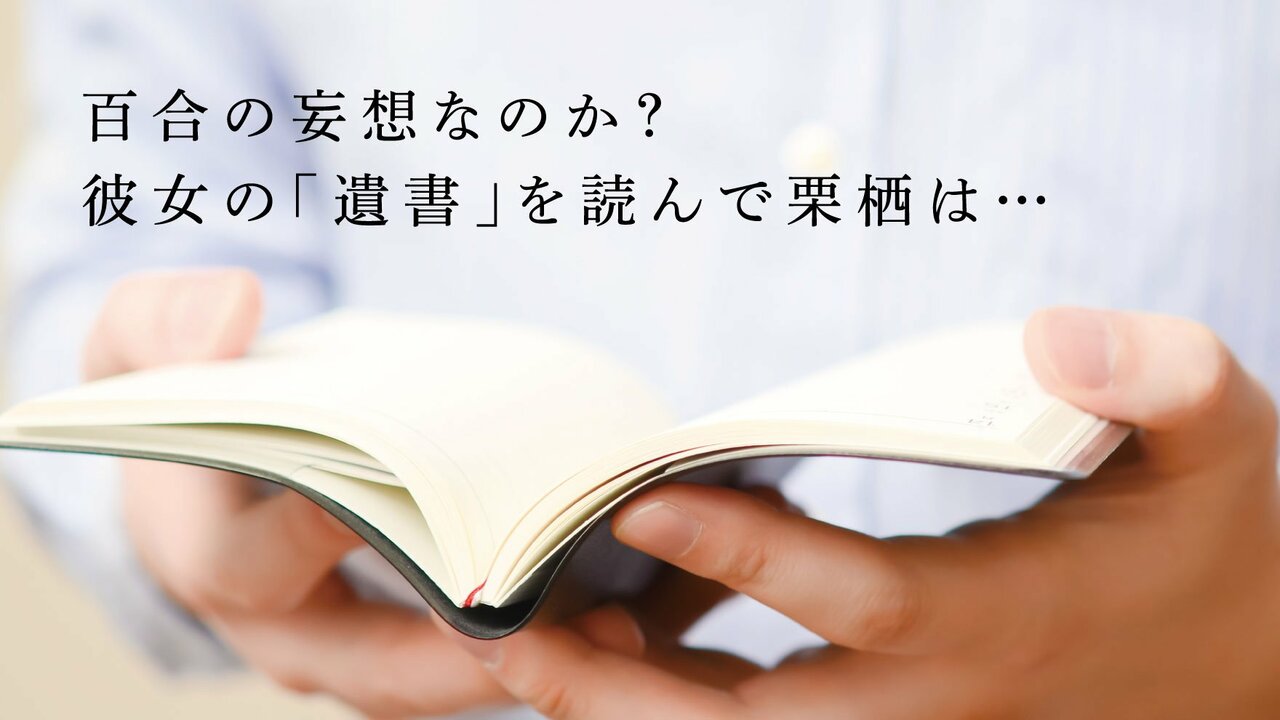Ⅰ
何か彼女が形見になるようなものを贈りたがっていたというような箇所を読んだ来栖は、このようなことを額面通りに受け止めてしまえば、百合ではなくてむしろ彼自身のほうが虚栄心に駆られて百合をそのように仕向けていると受けとめられてしまうだけではないのかと考えた。
そうかと思えば、これは彼女の不安定な精神状況での妄想ではないかと判断し、具体的に二宮家からこれに関して何か問い合わせなどが来れば、応答することなど避けるよう努めなければとも考えた。
夢を百合は見て、その中で間もなく死んでしまうのだというようなお告げを聞いてしまっている。
それは春から夏にかけての季節の変わり目であったようで、彼が二宮家を訪ねた時の母親の回想では、これを契機に彼女は以前にも増してひっそりと、世間から引きこもった生活をするようになったということだ。
そして秋に入ってから、再度死を告げ知らせる夢を見てしまう。
この時点では彼女はこれまで通り考えたことや思ったことは両親に全て話していた。しかし、彼にこがれているという気持ちについてだけは、彼女は全く何も打ち明けなかったとのことだ。
両親のほうも春先までは娘が健康そのものだったと見ており、亡くなってしまうなど全く予想だにしなかった。
だから娘が時たまふさぎこんでいるのを目にするようになっても、遅ればせの思春期を迎えているようだと、半分冗談交じりで受けとめ、彼女が少し放心状態の様子をくり返し見せても意に介さなかったとの由である。
彼女の家族に会って話を交え、彼女の『遺書』を読んで理解した限りでは、来栖はこれだけのことを知ったことになる。
その後二宮家のほうから来栖に連絡してくることはなかった。
彼のほうもことさら何かの用向きを見つけ出し、百合の母親や兄にコンタクトを取ろうというような気持ちには全くなれなかった。
しかし百合のことだけは一人で手持ぶさたの折など、どういうわけかふと思い起こすような時が出てきた。生前には全くと言っていいほど没交渉の相手であったし、百合という存在がすでにあの世の者で、この世の尺度ではもう存在していないのに、思い起こすこともあるとは解せないことだ。
かつて生者であった者の死者としてのありようというものなのか。
そのような彼女が心の片隅に住み着いてしまっているのだと、来栖は支離滅裂で理屈に合わないことまで思いつく始末だ。
このようなことを考えてしまう事自体が不思議といえば不思議で、そのようなことを思いめぐらすことこそ忌々しいと感じ、心の中から追い払おうとする時もある。彼女の姿形全体については記憶からどんどん失せていくところが多かった。