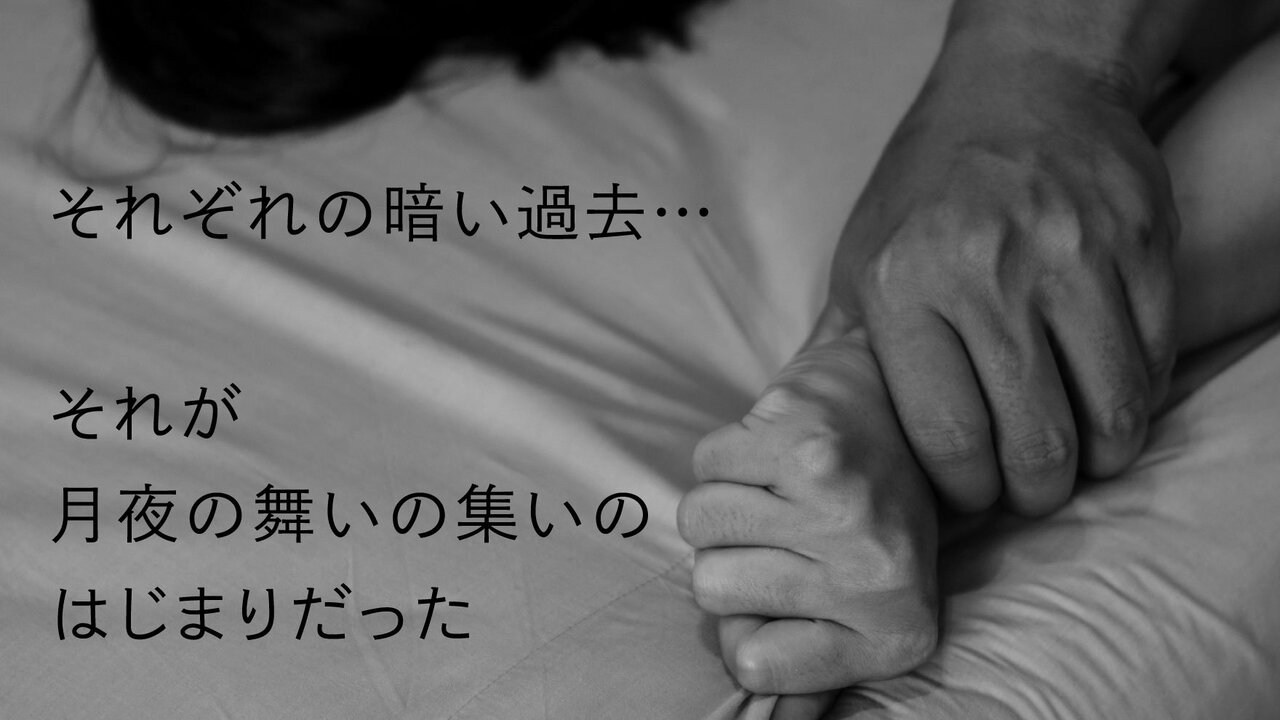五人の女性たちは現代日本のどこにでも一般的に見られるような、取り立てて特殊な問題もない普通の家庭の中に育っていた。ただ少し違っていたのは、男性不信の念がいく分か強いことだった。
そんな自意識から、女たちだけの生命のために、月夜の舞いに集うという別荘の案内板に興味を惹かれ、男性を排することを第一に表明した潔さに心を動かされたのだった。
そして、実際に面談した当の高弥さやの、予想外に美麗な容姿と気品と色香を持ち合わせている風貌に、同じ女として感嘆し、信頼することに誇りを覚えたのだった。
およそ二十年の年齢差をこれほどに美しく、あでやかに保って生きられるものなら、この人をお手本として見習いたいくらいに、思わせる魅力があった。五人の舞姫たちは、しかし女として極度の痛手をこうむって致命傷となるほどの経験があるわけではなかった。
男性一般に嫌悪を覚えるほどではなく、成育過程で男子たちに嫌がらせをされたり、侮辱されたり、無視されたり、薄情な行為をされたり、つまり不快な思いを、より強く根に持っていることが、不信の念を形作っていたのにすぎなかった。
だから将来に結婚を考えないのでもなかった。彼女たちはそれぞれ、一時しのぎの派遣やパートやアルバイトなどの勤め先を持っていた。
芹川郁代は、町内の小学校の給食調理、町宮菊絵は、ビデオショップの貸出し受付、小竹悦子は、大型書店のレジや書籍の受注管理、北上あやは、美容関係のコールセンターの電話オペレーター、植森朱美は、百貨店内の婦人服売場の店員、いずれも、企業の正規雇用の束縛をあまり望まず、自分の生活習慣が会社勤めで堅く固まってしまうような、正社員になることに意志がすんなりと進まないためだった。
高弥さやは幼少期から、クラシックバレエと日本舞踊の両方を習いながら育ち、高校生の頃には両方の稽古場で相当の上達を認められていた。クラシックバレエでは国際コンクールなど実際的な目標を考えられるほど先生に褒められ、日本舞踊では師匠と二人で舞台に並び、稽古の成果を披露するという希望が一度だけ特別にかなえられたことがあった。
しかし高弥さやにとっては、それくらいでもう充分に望みが達成されていた。
さらに周りの人たちから過大な評価や期待を寄せられたり、熱心に応援されたりするのを好まず、また脚光を浴びたり、あまりに晴れがましい舞台に上がりたいとも思わない性格だった。