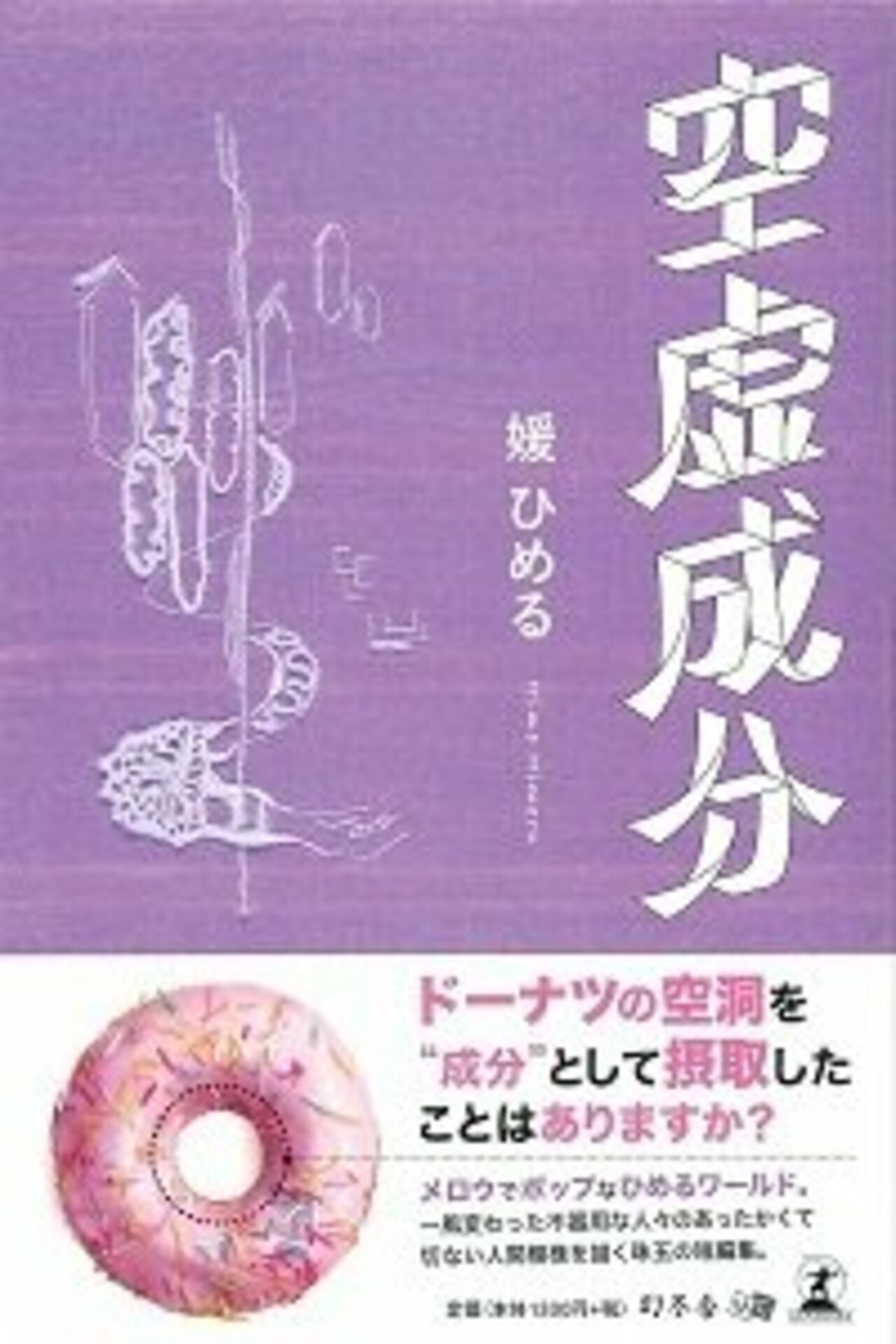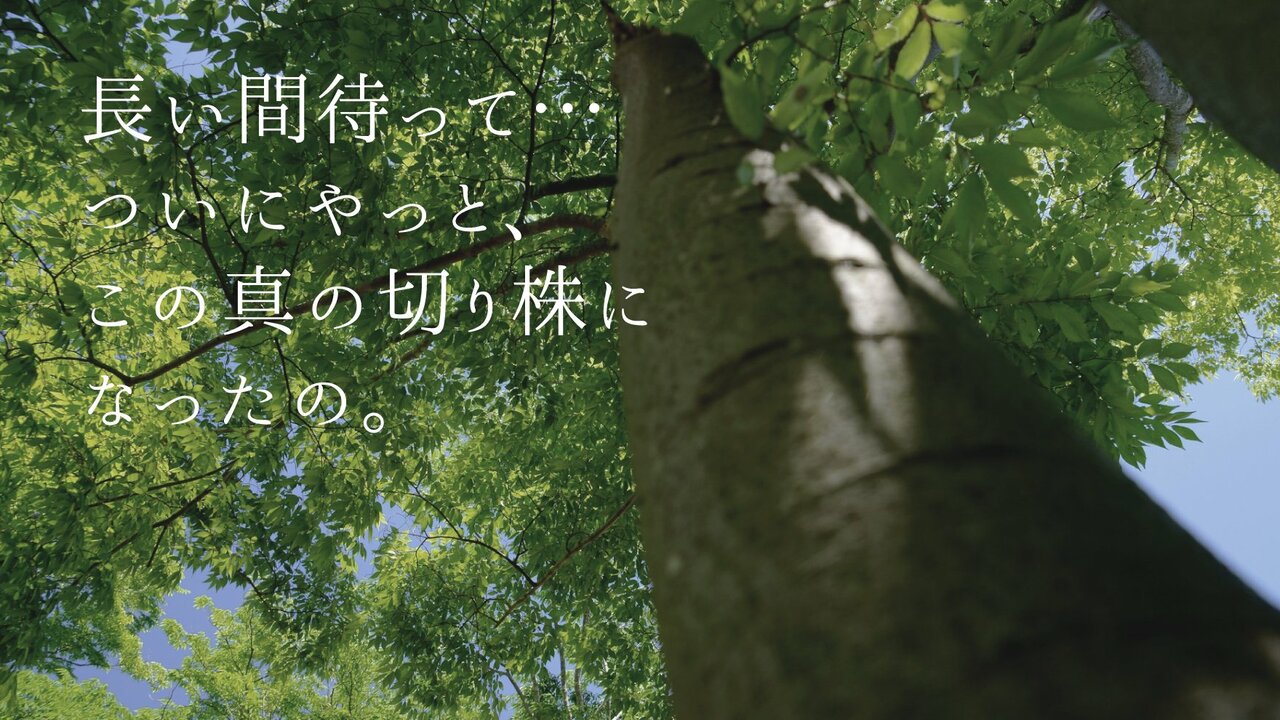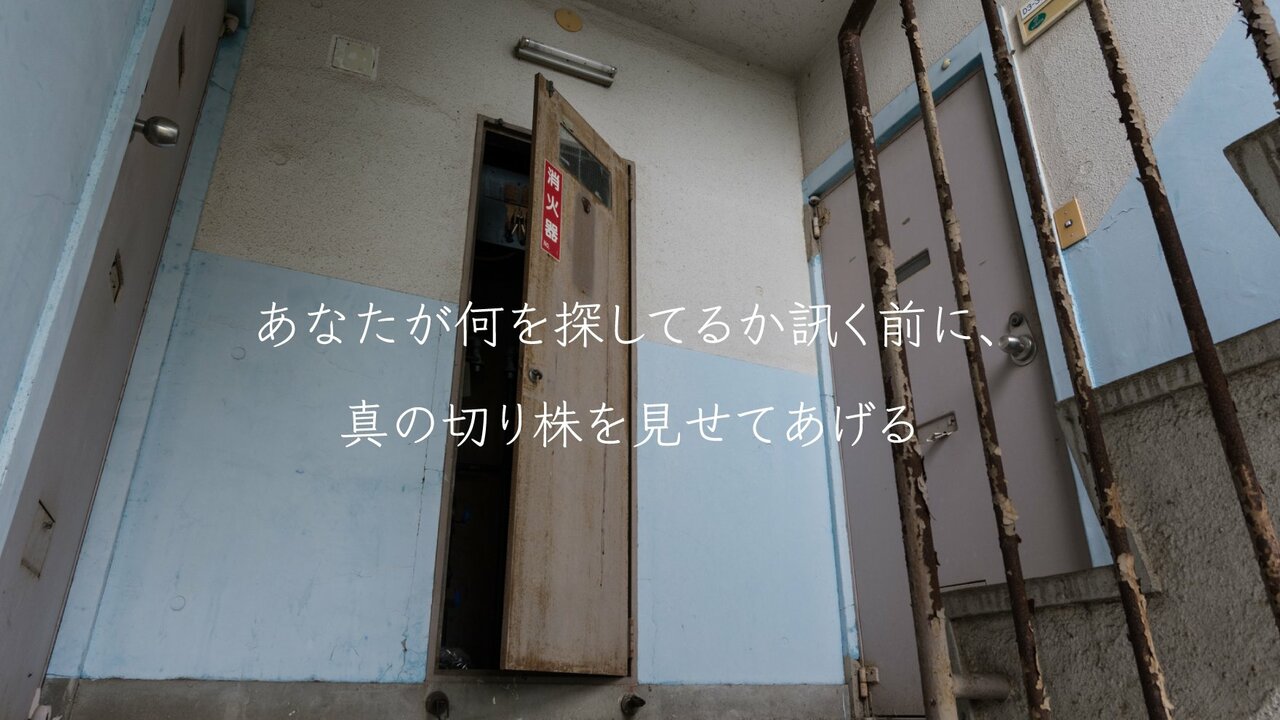コンビニにて
コンビニは、家から歩いて十分ほどのところにある。そこのコンビニは、入るといつもヘンテコな臭いがする。時間の経ったおでんの汁の匂いと、よく洗っていないダスターの臭い、あとそれらをむりやり帳消しにしようとする消毒薬の臭い。
【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。
その三つが同じ強さで喧嘩し合っているみたいだ。華はもちろん、その臭いが好きではない。だが臭いがするのは入口だけなので、息を止め、カゴをひっつかむと、素早く店の中に足を進める。そして菓子の陳列棚の前に行く。
カゴの中に目についた菓子をぽんぽんと景気良く放り込んでいく。華の嗜好は決まっていて、買うものはだいたいいつも同じだ。カゴに山盛りに物を入れると、レジに行く。
たまに訪れて大量に菓子を買っていく自分のことを、きっと店員は覚えているに違いない。もしかするとコンビニ内で、自分はちょっとした有名人になっているかもしれない。ほらまたあの子が来た、と密かに噂されているかも……。
ぐるぐると思考が勝手に回り始めて恐ろしくなってくるので、そういうことを考えそうになると、華は脳の一部を強制的に停止するようにしている。店員の顔は決して見ない。
声で、男か女か、年寄りか若者かを知る。レジで勘定を待っているあいだ、カゴの中の品物が店員の手でどんどんビニール袋に移されていくのを、華はぼんやりと見ている。
ありがとうございましたぁ。いかにも習慣的な、心のこもっていない声を背に、彼女はコンビニを出る。一歩足を進めるごとに、膨らんだビニール袋がふとももや脛に当たってシャリッシャリッと音をたてる。
コンビニのビニール袋がたてる音は、もしかすると世界で一番生活感があふれている音じゃないだろうか、と華は思う。そんな音をさせながら道を歩く自分を恥ずかしく感じる。