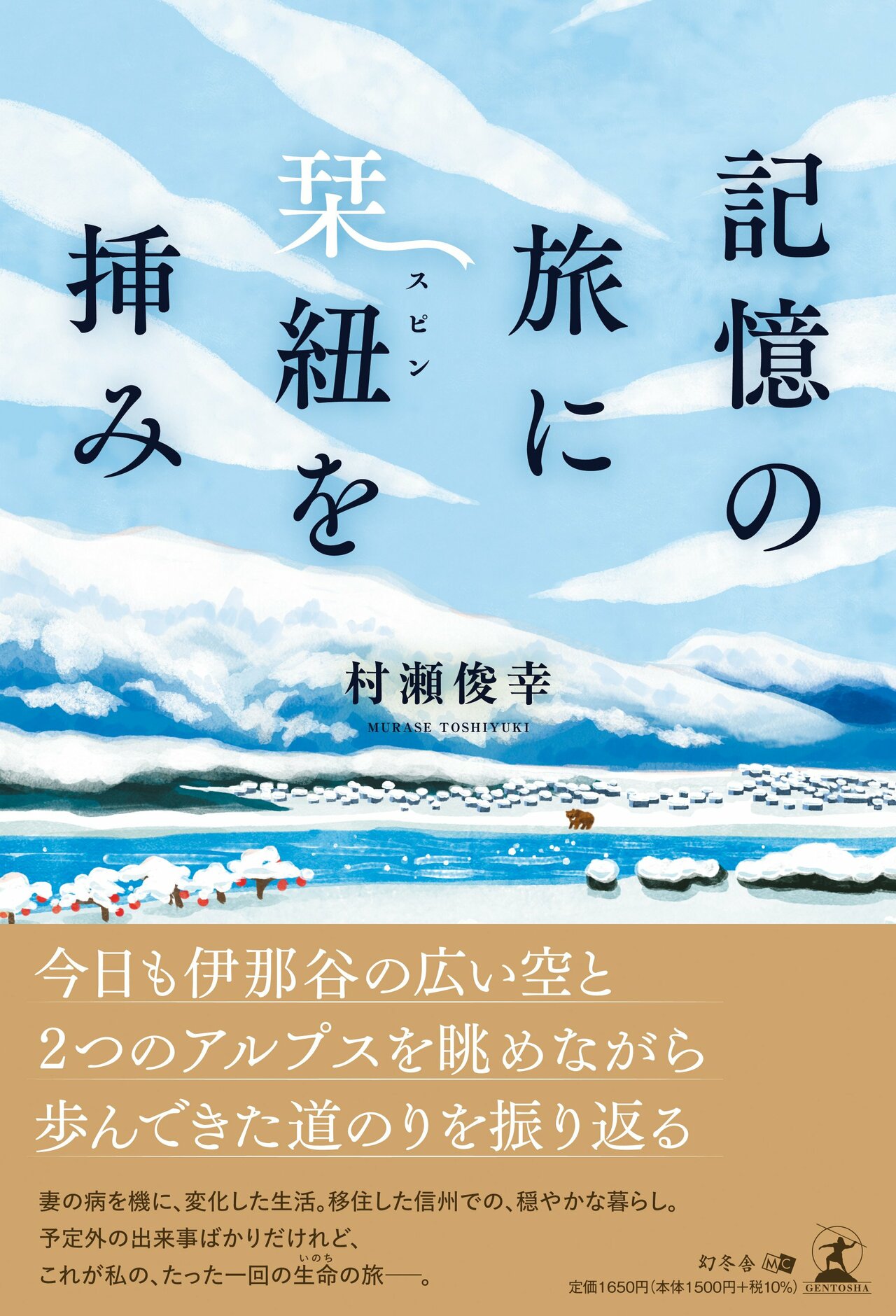友達はもう一人の友達に耳打ちすると二人で、私をどんどん彼女のほうへ引っ張っていきました。私は恥ずかしいやら、かっこ悪いやら大混乱していました。
「こいつが踊りたいって言ってるから、踊ってやってよ」
彼女が他の相手と踊っている前までやって来て、友達は勝手にどんどん話を進めていきます。
「別にいいよ。代わってくれる」
彼女は、相手にそう宣言すると私と向き合いました。
私はその声が信じられませんでした。聞き違いに違いありません。でも状況は私の思いとは違うようです。もう後戻りもできません。彼女の相手をしていた同級生も私の友達も、二人を残してさっさとどこかに行ってしまいました。
どうしたらいいかも分からず、ただただ焦って突っ立っていると、彼女がちょっと戸惑いながらも右手を差し出して言いました。
「私の手を握って、もう片方の手は私の背中に回して」しっかりした声で教えてくれました。
どんな音楽だったかもう覚えていませんが、スローなちょっと儚(はかな)いメロディが始まりました。もう周りのことは全く見えません。彼女の声がしました。
「ねえ、もうちょっと他のみんなのように動いてくれないかなあ。私が動くから合わせてきてね」
それから必死に彼女に迷惑にならないようにと、下ばかり見て足を動かしていきました。
時々彼女の足を踏んだり、バランスを崩して彼女の胸に微かにふれたりで、緊張の連続でした。ようやく曲が終わり手を離すと、手のひらはじっとりと汗ばんでいました。半袖のカッターシャツの背中にも、汗が流れていきました。
「暑いね」
彼女は苦笑いでした。
卒業が近づき、どうしても自分の思いを伝えたく彼女に電話をかけました。彼女にはその時、好きな子ができたという噂がありました。それならそれで邪魔をする気持ちはありませんが、好きだったということだけは伝えたいと強く思っていました。