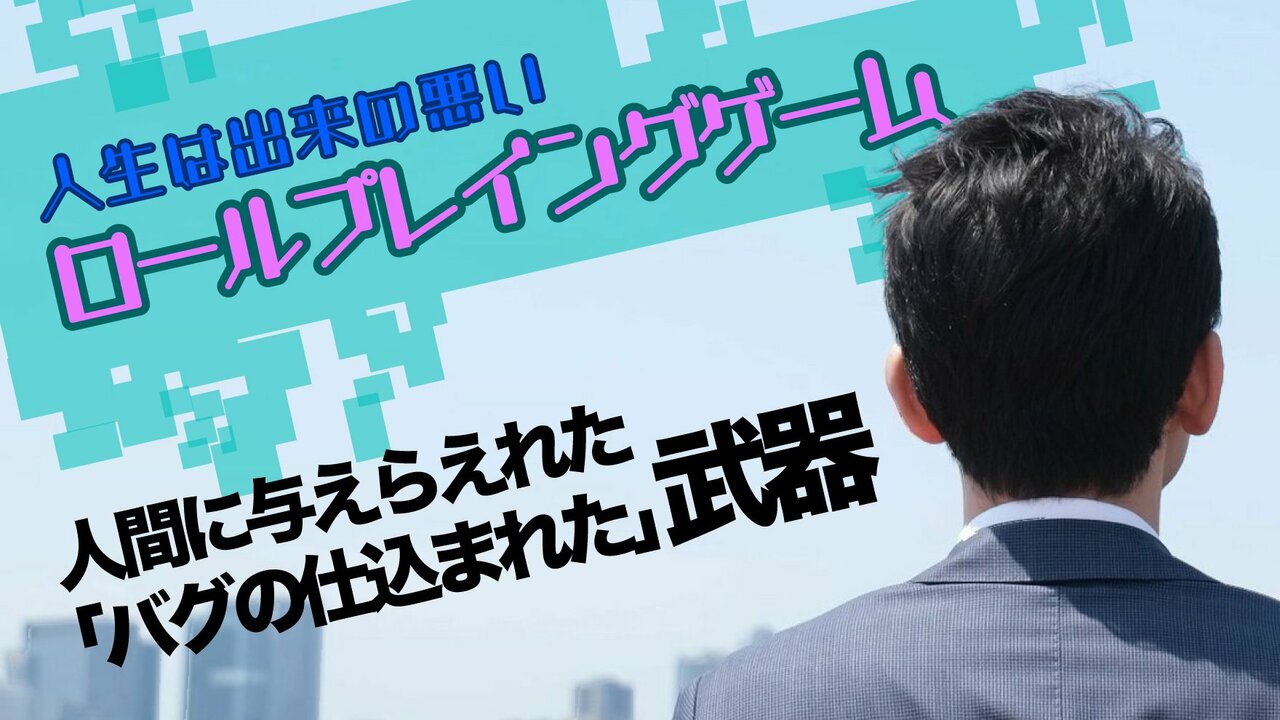自由における次なる敵は、人間よりもずっと絶対的であり、同時にこの世の何物よりも抽象的であるという非常に厄介な相手だ。
それは、生に対して常に影のように寄り添い片時も離れることがない「死」という怪物。
他者は僕「から」自由を奪う存在であるとするならば、死は自由を認識する僕「そのもの」を抹消するものだ。死の最大の問題は、その容赦ない非回避性にある。人間からは隠れることも逃避することも可能だろう。それは単に心掛けの問題だ。
だが、死からは何人たりとも逃れられない。未だかつて死ななかった人間はいない。人生は常に死への旅路の途上であり、我々は死に対して一切の拒否権を持たない。その意味で、死はこの世における数少ない真理だと言っていいだろう。
自由は生の内側においてのみ成立する。「死後の自由」は空集合だ。その前提に立つならば、僕たちが認識する自由は、生の檻の中でだけ存在可能な概念であって、その頑丈な鉄格子の外側には、人間の認識を断固として拒む「生に非ざるもの」という断崖絶壁が控えている。
人生における自由はあらかじめ死によって時間的・空間的にタガが嵌められていて、ある日突然、舞台の底が抜けるように、僕という認知のプラットフォームごと崩落するように設計されているのだ。この生の舞台の上映時間を把握しているのは――もし存在するのならば――神様だけだ。
演者であり主人公であるはずの僕は、この人生という寸劇がいつどのように終幕するのかを知らない。輝かしい未来や安らぎの老後を夢見ながら、明日には死んでいるかもしれないのが人生だ。絶え間ない断絶への不安と陶酔の中で、僕は死ぬまで自分の人生を踊り続ける。