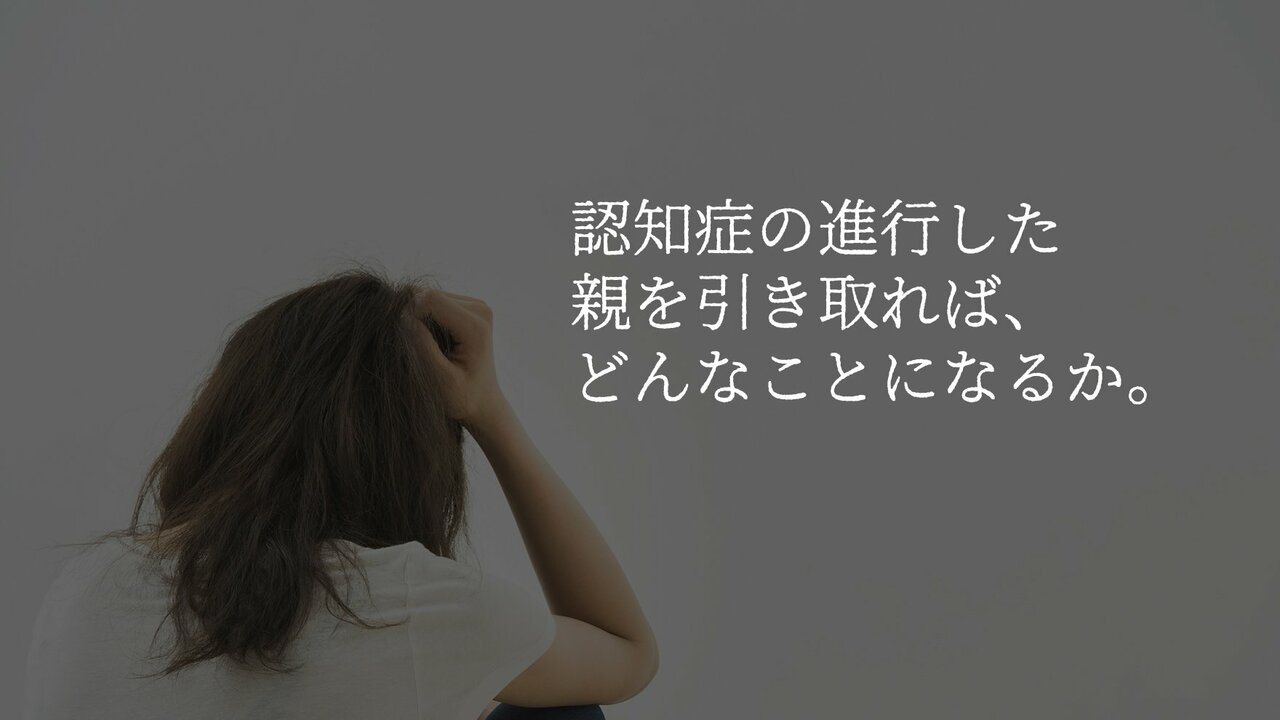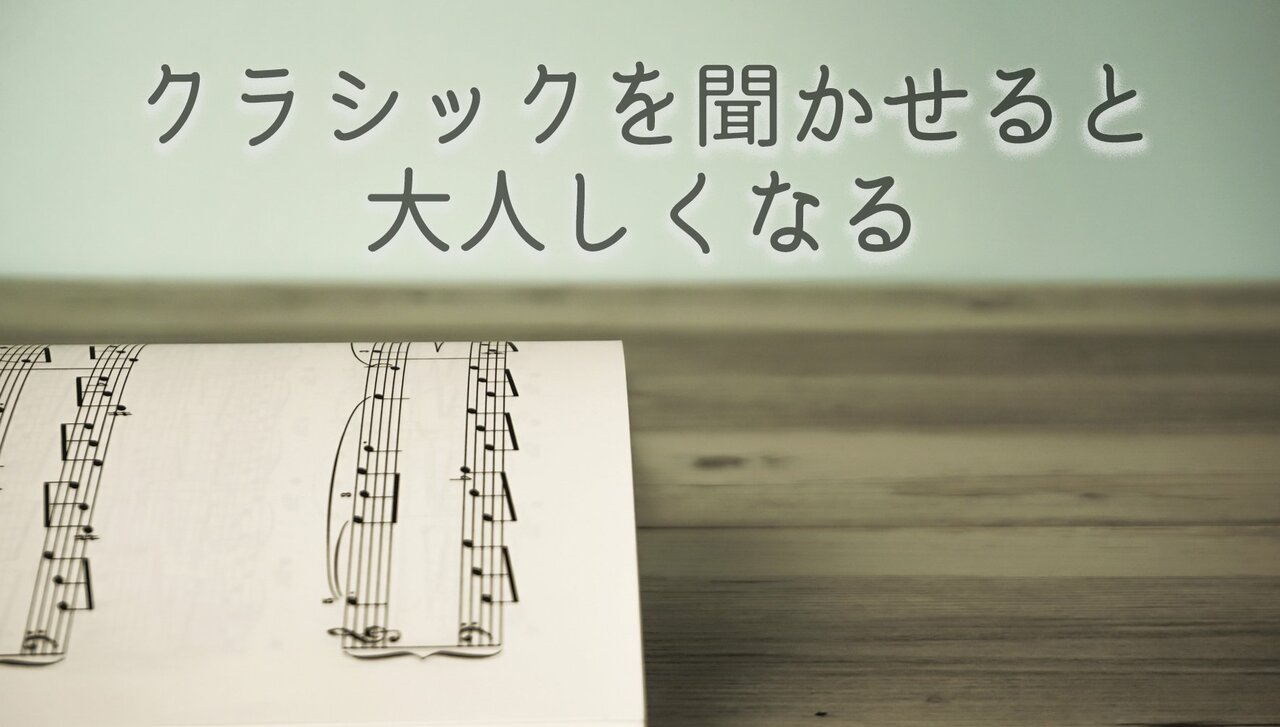第9章 祖母、父母の老いと死:孤独死を考える背景
1 祖母の終末:悲しみの思い出
20年の後に
それから20年あまりが過ぎて、わたしは2度目の学生生活を医学部で送っていました。
在宅医療の授業だったか、それともガンについての授業だったか、講師が末期ガンの在宅医療・介護について語っていました。在宅というと痴呆(認知症)が取り上げられることが多いけど、その講師によれば、在宅医療・介護に向いているのはむしろ末期ガンの方であるらしい。なぜなら、末期ガンの介護は「終わりが見えているから」。そして、こんなことを語った。
「人間は、3ヶ月とか半年とか、期限が見えている苦労なら、かなりの苦労にも耐えられる。だから、末期ガンの患者の介護は家族も頑張れる。それに比べ痴呆の介護は終わりが見えない。いつまで続くか分からない苦労は人を絶望させる」
この言葉を聞いて、わたしはすぐに20年前の出来事を思い出した。ほかの学生たちはどんな気持ちでこれを聞いていたか分かりませんが、わたしは実感と共感を込めて聞きました。そうなのです。終わりの見えない苦労は人を絶望させる。
そして、そんな苦労を引き起こす者への憎しみと怨みをかき立てる。終わった後になって振り返れば、怨むのも怨まれるのも、どちらも悲しいことなのだけど。
2 父と母:安らぎ
親の死を想定して
祖母の死から30年以上が過ぎた2008年の年末、久しぶりに福岡に旅行して、実家に顔を出しました。わたしは医学部を卒業して医者になり、10年ほど経っていました。
実家の両親は元気なようでした。母は81歳、父は85歳。二人で生活するには不便はないようですが、「年相応の」軽い認知症は既に始まっています。
特に母は明らかで、一緒にいると10分に1回は「ゆたかは今年でいくつになったか?」と聞くので、そのたびに「52歳ですよ」と答えます。「もうそんなになるか」と感心してくれるのですが、また10分もすると、同じ質問を繰り返します。そしてわたしは同じ答えを繰り返す。
毎日ならうんざりするかもしれませんが、年に1回くらい、それも2~3時間のお付き合いなら苦になりません。父はまだ母ほどにはボケていないようですが、多少の記憶の混乱はあるようです。
ともあれ、お昼ご飯をごちそうになりました。もっとも、作り付けの煮付けなどを電子レンジで温め直してお皿に盛ってくれるだけの簡素な昼食ですが、そういう簡単な家事をしている時の母の動きは、はたで見ていても少しも危なげない、手慣れたものでした。
温め直してくれた煮付けも、もちろん総菜屋で買ったものではなく、前日か前々日くらいに母が自分で作ったものです。多少ボケてはいても、狭い世界で日常生活を送るには何の支障もないようでした。