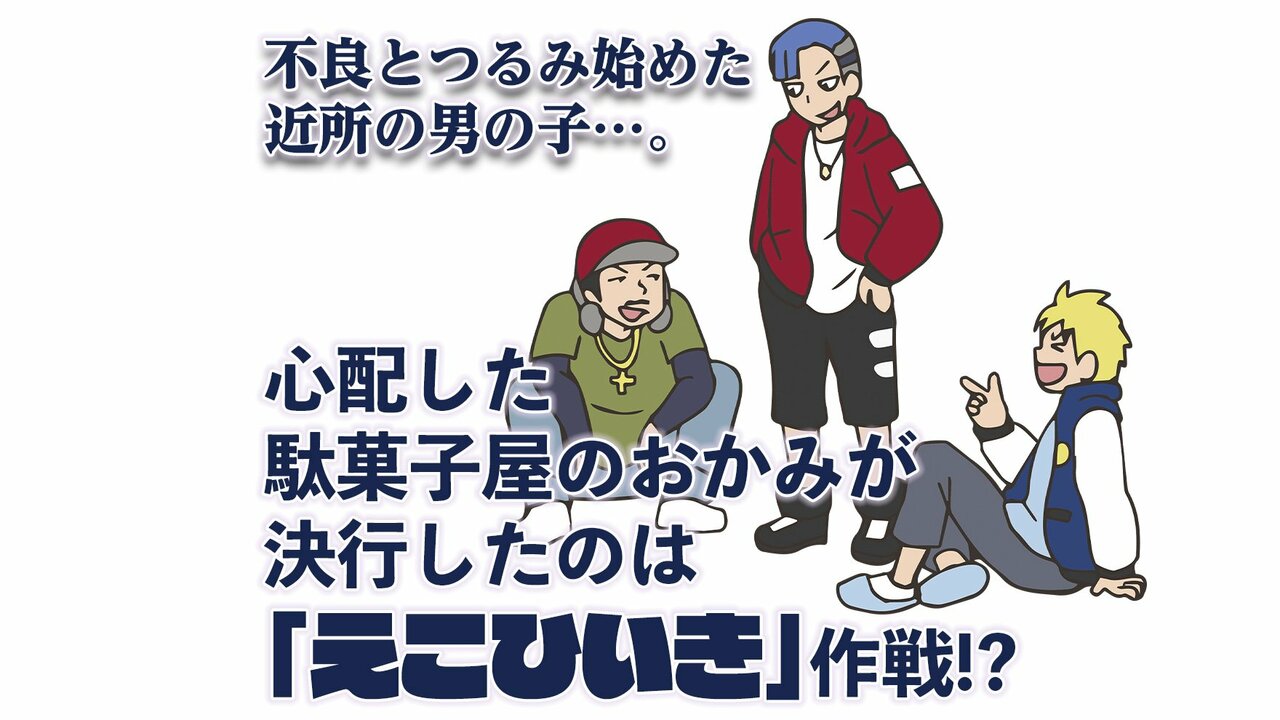第一章 激変した幼少期
「大きくなったら、自分が母を支えなくてはならない」と、渉太郎は荊(いばら)を負う決心を心の内にした。
和子はもともと健康に不安があったことに加え、このときの苦労が原因で、その後の長患いによる苦しい病相の生活を送った。この頃の和子は、暗転した生活を子どもにまで強いてしまった憶測の情からか、渉太郎に諭すように言葉を何度も紡いだ。
「大学を出たら自分で生業を決して興してはいけない。大きな会社に入って経済的な苦労を家庭にかけないようにしなさい。勉強だけでなく芸術にも親しむ生活を送りなさい。そして結婚するなら賢い女性をもらいなさい」と言うのが口癖となっていた。
和子は渉太郎に処世訓を遺して人生を生き切った。母の願いは渉太郎の骨身に沁みて生き続けることになる。
渉太郎の両親は教育者と政治家の家系であった。生まれ育った環境と裏腹な人生を送ることなどまったく考えもしなかったはずである。生きてきた姿勢や人生態度に関係なく、つまるところ結果によって人の幸せは運命的に決定づけられる。
渉太郎は、「飢えた子どもに文学は必要なのか」との厳しい現実の中にあって、勉学に勤しむことで苦しい幼少期を慰藉(いしゃ)することができた。後年、大学を終えると、学生には人気の高かった会社に入社することができた。渉太郎は教育と勤勉によって、少年の日の誓いを守ることができた。
入社してからあっという間に一年が過ぎた頃、上司から、
「アメリカに出張してきなさい」
と、突然言われた。
仕事で多少英語には関わってきたものの、会話にはまったく自信がなかった。上司はその不安な表情を見透かすように、
「会社が君の将来を見込んで、投資してくれると思いなさい」
笑顔を浮かべながら優しく言葉をかけてくれた。
「ホームビデオ訴訟についても勉強してほしいが、こちらはあくまでも余裕が有ればの話だがね」
過度の期待を渉太郎にかけない上司の思いやりと受け取れた。
渉太郎は上司からアメリカ出張を伝えられたとき、母の夢をも叶えられると気負った。早く現地に慣れ、いつでも赴任することができるようになりたいと心密かに願った。
初めてのアメリカ出張は、航空会社に勤める妻からアドバイスをもらい、使い古した日英と和英の両引き辞書GEMを借りた。
寝る間を惜しんでの懸命な英会話練習の毎日であった。まさに、「習うより慣れよ」のごとく現地体験が功を奏したこともあり、数カ月後には帰国しても良いとのファックスを受け取った。あまりの嬉しさに妻に国際電話で帰国日を知らせた。